ミャンマー進出・投資のポイントを本気で解説(第3回:人事が成功の可否を決める。新興国ビジネスを経営出来る本社体制とは)


ミャンマーへの進出・投資を検討する際のポイントを徹底解説。
第3回となる今回は、ミャンマーの人事、特に駐在員人事を中心に取り上げていく。
これまでの2回では、ミャンマーに参入する必然性、また参入する際のポジショニングについて解説してきた。いざミャンマー市場への参入・立ち位置が決まったら、いよいよ人事の選定という日系企業にとっての最大の難関が待ち受けている。
<ミャンマーへの駐在員派遣のポイント>
ミャンマー市場への新規参入にあたって、どのような駐在員を派遣すべきかとの相談を受けることがある。投資規模や業種業態、派遣人数にもよるので一概には言えないが、個人的な回答としては概して中堅社員が適していると考えている。年齢としては、平均的な日系企業における30代から40代前半のイメージだ。
30代に海外現地法人のトップを任せるというのは多くの日系企業にはチャレンジングな判断かもしれない。ただ、年功序列の日本社会では年齢や社歴がモノを言うものの、海外ではこのような考え方は無い。極端な例ではあるが、フランスのマクロンは39歳で大統領に就任し、フィンランドのサンナ・マリンは34歳で首相に任命された。30代で国家を率いてる現実がある中で、若手にトップは無理だ、などと言っていては海外市場ではそもそも通用しない。
海外子会社のトップに立つためには、当然業務面における専門性、経験、実績が一定程度求められる。そうしたバックグラウンドが無ければ、自社内のみならず、現地のビジネスコミュニティの中でのリスペクトが得られないからだ。従って、20代では現実的に難しいだろう。一方、50代の中には、サラリーマンとして上がりきった意識を持った(社内で上を目指すモチベーションも、自己向上意識も失いきった) 人が多いのも日系企業の現実だろう(当然、優秀な50代の方も中には多くいらっしゃるが)。中堅社員というのは端的に言えば、こうした背景による。
もちろん実際には投資規模によっても異なるだろう。大規模なM&Aによる市場参入や、大型の投資を伴う工場建設・インフラ開発などの場合には、本社役員との日常的な意思疎通が求められる中で、中堅社員には荷が重い可能性もあるかもしれない。ただ、新たにゼロベースで100%子会社を、例えば投下資本100万米ドル以下程度で進出する場合は、中堅社員に任せた方が良いケースが多そうだ。私自身も、大手証券会社の現地法人(100%子会社、資本金50万米ドル)の社長を任されたのが35歳であったが、曲がりなりにも周囲に助けられ何とか乗り切ることは出来た。
確かに人生100年時代においては50代も若手という考え方もあり、年齢で全てを判断するのは明確に間違っている。ただ、重要なことは、これまで誰も歩いたことが無い道を突き進んでいく、そうした答えの無い環境で求められる「突破力」を持っているか否かだ。高い壁に直面しても、あらゆる手を尽くしてよじ登っていく、或いはハンマーを持ってきて壁をぶち壊す、程の突破力が必要であって、日本の年功序列システムの中でシニア人材がそうした気力を残していることは残念ながら少ないとは思われる。
また、ミャンマーへ異動させる人材の適性の観点でよく見られるのが、周辺国からの横移動だ。ベトナム、タイ、インド等からの人事異動の割合が特に多い。これは、新興国市場における経験が類似マーケットで活かせるだろうという推定に基づく判断だろう。
もちろん、新興国市場での経験自体はプラスに働く部分はあろう。日本や欧米先進国にしか行ったことが無いような人材であれば、そもそも新興国での生活自体に苦痛を覚える可能性もある。また、新興国の人材マネージメントという意味でも共通して活用できるノウハウはあるかもしれない。
ただ、ビジネス慣習等の面で言えば、フロンティア OF フロンティアのミャンマーにおいては独自の色彩が極めて強く、ベトナムとの比較感でもビジネスを行う基盤が全く異なる。そうした意味では、周辺国の経験が活かされる割合は全体要素の中でわずかと言って良いだろう。個人的には、周辺国からの横異動を前提にスクリーニングする方法は如何なものかと思う。
<ホウレンソウ(報・連・相)という悪しき習わし>
海外市場、特に新興国市場を日系企業が攻略する際の大きな障害の一つが、いわゆる「ホウレンソウ(報・連・相)」だろう。多くの日系企業では新入社員時代に叩き込まれ、日本社会で働くための言わば常識・ご作法だ。
だが、日本と全くビジネス慣習が異なる新興国市場で、かつ本社の関連部門の多くの人が現地マーケットにかかる知見がほとんど無い中で、果たしてこのホウレンソウが機能する事例が一体如何ほどあるというのだろうか。冷静に考えてみて頂きたい。
海外子会社とは言え、現地においては社長がその企業の代表者だ。代表者が権限を持っていない中、或いはその場で決められない中で一体誰が相手にするというのだろうか。現地トップは、日々移り変わる事情の中で常に総合的な判断が求められる。その個別の事情を本社にいちいち報告・連絡するのは現実的には無理だ。それが前提だと言うのであれば、おそらく現地法人社長の仕事はそれに終始することになるだろう。実際それに近い状態の駐在員も見られる。そこには何の生産性も無ければ、誰も何の得もしていない。
非常に些末な話になって恐縮だが、日常感を出すために私個人の例を取り上げたい。私が現地法人の社長を務めていた際に、新たなオフィスの内装を手配していた。内装費用として予算を数百万円計上し、それに基づきほぼ計画通り進めていた。ある時、予算に含めていた壁のペインティングはオフィス全体の雰囲気上好ましく無いと判断し、それを取りやめた。代わりに現地の画商で、外部から訪問して頂いた人との会話になるような絵画を受付に置くことにした。その方がコスト面でも安く収まるとの判断だった。だが、この絵画の購入は本社に否決され、結局私が個人で購入することにした。否決の理由は、当初予算に含まれていないからだ。
これ一つを見れば誠に些細なことではあるが、現場で日々直面する判断に対して、本社からの不毛な意見が飛び交ってくることで、現場の士気は著しく乱れる。「だったら、全部決めてくれ」という声が、日系の海外子会社の至るところから聞こえてくるようだ。
日常的な取引先との交渉から資本・業務提携を意図した複雑な交渉に至るまで、それらの判断は常に状況状況に応じた総合的なものとなる。相手とのこれまでの貸し借り、今後の関係性構築、社内リソースの有効活用などを総合的に踏まえた発言をその場、その場で求められる。第三者には到底分かりようも無い。枠も与えられず交渉をして来い、などというのはパワハラのレベルとさえ言える。個別の現場判断が後々、意味不明な判断でひっくり返されることは、その人個人に留まらず、その企業の現地におけるレピュテーションにも影響することを多くの本社部門の人は分かっていない。
ホウレンソウを破り捨てることには大枠賛成であっても、そこまで任せられる人材が社内にいないとの話も出る。これに対しては、厳しいようだが、任せられる人がいない、または外部から採ってくることも出来ない社内体制なのであれば、そもそも海外進出は諦めた方が良いと思われる。
全ては人から始まる。商品・サービスの優位性も戦略も、全て人がありきの話だ。もちろん、派遣者を選んで、後は本社が全く関与すべきで無い、などと言っているわけではない。本社部門は自分たちの役割・位置付けを再定義するということが必要だろう。「管理」することは多くの場合何も生まない。「管理」の背景には、放っておくと現場が暴走するという固定観念が多くの場合含まれ、要は現場を信用していないことから生じている。ただ、信用出来ないのであれば初めから派遣してはいけない。
本来、本社部門はグローバルな戦略構築の中で、現場に対する「ミッション」を与え、それを実現する為の「支援」を行っていくのが役割だろう。「管理」が楽なのはよくわかる。私自身も、本社の経営企画部門で、管理だけに捉われていた時代が長かった。それで仕事をした気になっていた。だが、ミッションも与えられず、孤軍奮闘する中で後ろから縄を掛けられる現場の気持ちを推し量りたい。繰り返しになるが、そうした体制が取れないのであれば、初めから海外進出はしない方が賢明であるとすら感じる。
<ミャンマーにおける現地人事のポイント>
現地へ派遣する駐在員を決定した後は、現地法人の中での人事体制の構築が次の課題となる。簡潔に言えば、如何にして現地法人トップの負担を減らし、フリーにするかがポイントと言える。フリーにした途端、何をやって良いか分からず、仲間内のゴルフに明け暮れるような事が生じるのであれば、それはおそらく人選段階で間違っている。
フリーにするということの意味合いには、本社に対する不毛なホウレンソウを軽減するというだけでなく、現地法人に何から何まで社内で処理(自分で対応)することを押し付けないことが含まれる。特に日系企業の場合、経費抑制の観点から、社内業務をアウトソーシングすることを良しとしないケースが多い。許認可取得から、会計処理、給与計算に至るまで自社内で処理しようとする。日本人お得意の根性論に近い。またそれらが自分の仕事だと思い込んでいる現地トップも見られる。こうした勘違いが生まれる背景には、先に挙げた「ミッション」が不明瞭なケースが多いと言えるだろう。
何故これが間違いと言えるかといえば、明らかに費用対効果が合わないからだ。現地法人トップにかかるコスト(人件費、社会保障、住居費、車、保険等)が仮に年30万ドル、年間250日の勤務日とすれば、会社としては1日当たり最低でも1,200米ドルの付加価値を上げてもらわないと割りに合わない。1日8時間勤務とすれば1時間で150米ドルとなるが、ミャンマーで毎時間それだけの付加価値を出し続けることは至難の業である。そのような中にあって、慣れない業務を押し付けて、或いは非効率な作業を強要して、一体何を成し遂げようと言うのだろうか。正に本末転倒ではなかろうか。
ただでさえ、ミャンマーでは経済が対外開放されて日が浅く、現地の人材マーケットにおいて、ミドルマネージメント層が圧倒的に不足している。従って、日本人管理者が日々のオペレーションの品質管理(クオリティコントロール)に相当程度の時間を注ぎこまざるを得ない事情がある。そのような中では、現場の経営者が行う業務範囲を良い意味で本社が定義(コントロール)しなければ全体としての最適化は図れない。
感覚的な話とはなるが、現地トップの時間の使い方としては、「外部対応(顧客訪問、取引先の対応等)が3割」、「社内対応(社内会議、社員への指示・管理等)が3割」、「作業(資料作成、ルールの考案等)が3割」、「本社対応(本社への報告)が1割」程度が理想的な配分かもしれない。私自身も日系の現地法人で社長を務めていた際は、この割合を意識して定期的に自らの時間配分を見直すようにしていた。放っておくと、どうしても作業や本社対応の割合が高くなってしまうことが経験的に分かっていたからだ。
<ミャンマー現地法人の経営を通じた人材教育>
くどいようだが、海外進出で最も重要なのは人材だ。現場を任せられる人材が選べないのであれば、進出自体を諦めるのが得策だろう。そして、この人選にあたっては素養も重要であろうが、もう一つ忘れてはならない事がある。それは「本人の意思」だ。
通常、新興国での勤務は危険地手当(ハードシップ)が支給される。このハードシップは、不便なところに行かせる事の代償的側面がある。ハードシップの制度自体は良いとしても、その背景に「こんなところに行かせて申し訳ない」という企業側の考えがあるのだとすれば、或いは派遣される本人が「ミャンマーに来させられた」などという思いがあるのであれば、それはやはり間違っている。来させられたと思っている駐在員、或いはハードシップを期待した駐在員が成果を上げられる事などあり得ないことは容易にお察し頂けるだろう。
ミャンマーの現地法人経営は、多くの場合ゼロスタートとなる。そこら中に地雷が埋まっている中を突き進む経験は日本国内ではなかなか味わう事は出来ないものだ。人材教育の観点からはこれほど適した環境は無い。本人にとっても大きな成功体験に繋がり得る。そこに望みもしない人材を当てるのは決して賢明な判断とは言い難い。
最後に、「駐在期間」についての私見を述べておきたい。通常日系企業では2、3年のローテーションが多く用いられている。だがミャンマーのような新興国においては5年は見ておくのが良いだろう。少なくとも現法トップについては3年では概して短すぎる。
現法トップは、その国における会社の顔だ。日本の上場企業であっても、2、3年で社長交代を繰り返す企業などほとんど無いだろう。それと一緒だ。
ざっくりとした期間の配分としては、例えば最初の1年はミャンマー市場に慣れる期間、次の2年は挑戦と失敗の繰り返しによりチューニングする期間、最後の2年は成果を出す期間、と位置付けるのが良いかもしれない。
また可能であれば、本人に対しても「特殊な事情がない限り、5年は代えない」と伝えておく方が望ましい。いつ代えられるか分からない中では長期の施策は取りづらい。
チャレンジングな経験を自ら望む中堅社員がいる会社は本当に強いと感じる。或いはそうした人材を育てていく事こそが海外進出の第一歩かもしれない。
関連記事 : ミャンマー進出・投資のポイントを本気で解説(第1回:ミャンマー市場の特徴。数ある海外市場の中で何故ミャンマーなのか) 2020年8月6日
関連記事 : ミャンマー進出・投資のポイントを本気で解説(第2回:参入市場の構造を理解。市場エコシステムの中でのポジショニングとは) 2020年8月9日
関連記事 : ミャンマー進出・投資のポイントを本気で解説(第4回:パートナー選定ミスは致命的。ミャンマーでの合弁会社設立の要点) 2020年8月15日


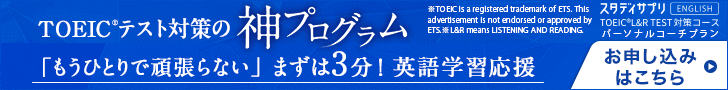



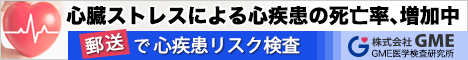













この記事へのコメントはありません。