ミャンマー進出・投資のポイントを本気で解説(第1回:ミャンマー市場の特徴。数ある海外市場の中で何故ミャンマーなのか)


ミャンマーへの進出・投資を検討する際のポイントを徹底解説。
第1回は、数ある海外市場の中で「一体何故ミャンマーを選ぶのか」、「ミャンマーである必然性はあるのか」、という点について市場の特性と留意点を中心に解説していく。
<ミャンマー市場への甘い期待が生み出した惨劇>
2011年の民政移管以降、ミャンマーはラストフロンティアとして世界の注目を集めた。欧米による経済制裁は段階的に解除され、日本からも多くの事業会社や投資家がミャンマーを訪れた。
2013、14年頃は正にブームの真っ盛り、日系企業の進出もうなぎ上りの状態であった。それはゴールドラッシュのように、ミャンマーにあたかも秘宝が眠っているかのような勢いであった。
※ 日系企業の進出企業数の推移は、こちらをご参照
株式市場におけるバブルとも似ている。実体経済とは無関係に、期待だけが先行、他社が進出するから自社も出るというような本質とはかけ離れた循環が形成された。
だが、2020年現在、ブームに乗って進出した多くの企業(日系のみならず外資系企業全般)は、現地ビジネスの中で苦境に瀕している。
では、ミャンマーブームに乗った進出・投資の一体何が問題であったのか、そこに甘い期待は無かったのか、或いはそこから学べることは何なのだろうか。もちろん成功に結び付いた企業もあるだろう、また事情は各社各様ではあろうが、ここではおよそ平均的な姿としての失敗像に迫りたい。
<通り一遍の「進出メリット」には何の意味も無い>
書店でミャンマー進出関連の書籍を目にして頂くと概ね以下のような「進出メリット・理由」が記載されているはずだ。
ネット上でもこの手の説明は多い。
(Ⅰ).中国・インドという大国に挟まれた地理的優位性。人口30億人に面した市場
(Ⅱ).人口5,400万人の消費市場
(Ⅲ).親日国
(Ⅳ).高い識字率
(Ⅴ).安価な労働力
実際の進出を考える際にこれらが如何に空虚であるかを以下説明していく。
まず、(Ⅰ)の所謂「地政学的」理由付け。どの書籍にもほぼ必ず書いてある。もちろん、ミャンマーの地理がマクロ面で優位なロケーションであることは事実であろう。
が、果たしてこのことが、自社のビジネス展開にどのような影響を与えるかを具体的に説明出来る人が一体どれほどいるだろうか。例えば、物流関連の事業、特にクロスボーダーの陸上輸送の事業展開を図ろうとする企業であれば関係する部分はあるかもしれない。或いは、ミャンマーでの生産物を隣国に輸出するような事業(そのような日系企業は現状無いが)は長い目で見て恩恵を受ける可能性が無いとは言えない。しかし、おそらく圧倒的多数の企業において、ミャンマーの地理は大した意味を成さない「メリット」だろう。
地理的な場所よりも、むしろ日本との時差や、日本からの飛行時間の方が、現実的にはよりビジネスに影響してくるようにさえ思われる。
(Ⅱ)は、5千万を超える消費市場という説明。ミャンマーの人口は周辺のカンボジアやラオスに比べれば多いが、東南アジア(ASEAN)諸国の中で決して目立って多いわけでは無い。インドネシアは別格としても、フィリピンは約1億人、ベトナムも9千万人超の人口規模を持つ。
人口のみならず、「消費市場」という観点で言えば、一人当たり所得についてもミャンマーはそれらの国を下回る。インドネシア、フィリピン、ベトナムのような国が既に経済の成熟段階にあるならまだ話は分かるが、各国とも絶賛成長中だ。その中で、一体何故ミャンマーなのか、という点には全く答えられていない。
また、そもそも日本の国土面積の1.8倍という広い面積を持つミャンマーにおいて、全国単位の人口を考える必要があるビジネスは限られているかもしれない。例えば、消費財関連のビジネスであれば、販売網(ディストリビューター)次第で、全土への展開も可能であろうが、多くのビジネスは経済都市ヤンゴンでの活動に留まる。この場合、ヤンゴンの人口約5百万人程をベースに考えるべきだろう。
長期的には全土への展開と言う青写真を描くことも当然必要なことではあろうが、まずは短期的に如何に事業を軌道に乗せるかということが軽視されるべきでは無い。
(Ⅲ)の親日国というのもよく語られる進出メリットの一つ。これについては、果たして本当に親日国であるのかということ自体にそもそも疑義がある。詳しくは、こちらをご参照願いたい。
(Ⅳ)の高い識字率について。
これもミャンマー市場の特徴としてよく目にするが、(1)そもそもミャンマーの識字率は相対的に高いとは言えない、(2)識字率が仮に高かったとしてそれが自社のビジネス展開上、具体的にどのように優位に働くというのか不明、 という二つの突込みをしておきたい。
(1)については従前からミャンマーの識字率は92‐93%程度と言われてきたが、これは東南アジア諸国の中で目立った高さではそもそも無い。また、ユネスコの最新データによれば、実はミャンマーの識字率は76%に留まるという報告もなされている。これが、事実なら「元の調査した奴、誰だよ」との怒りを覚える人もいるレベルだろう。
(2)の突込みに関しては、例えばミャンマーで新聞社を始めようと言うのであれば国民全体の識字率が重要なのは理解出来なくも無いが、現実的には多くのビジネスにとって、識字率が何かしらの影響を及ぼす具体的なイメージが全くわかない。
ミャンマーの高識字率の都市伝説は、ミャンマーの寺子屋制度から来ていると思われるが、ミャンマーの教育制度を俯瞰すれば、基本的には軍事政権の影響によって壊滅的に打撃を受けている。教育体制は、長きにわたって 低空飛行を続け、その間、富裕層の子女は海外に留学することで優れた教育機会を得てきたのが現実だ。あたかも教育水準が高いかのように捉えるのは、理解に苦しむ。
最後に(Ⅴ)は、安価な労働力。
確かに、周辺国と比較したワーカーレベルの人件費が現時点で相対的に安いというのは統計上は事実だ。ただ、これについても2つ反論をしておきたい。
1つ目は、この説明には多くの場合、生産性の観点が欠如していることだ。ミャンマーのGDP・所得は低いことから、人件費が一定程度相関して低いのは当然だろう。問題は費用対効果が高いのか否かだ。労働集約的事業であっても、やはり労働者の生産性の高低が事業のパフォーマンスに影響してくる場合は多い。この点、日系の製造業からはミャンマーにおける生産性は低いということを耳にすることが少なく無い。
2つ目は、ミャンマーでは近年のリベラルな政権運営(ポピュリズムの台頭) の中で 、最低賃金は急激に上昇傾向にあり、現状の低賃金水準が保てるか否かは怪しい情勢という点。最低賃金は、2018年にそれまでの日額3,600チャットから、4,800チャット(約3.4米ドル)に33%引き上げられた。ミャンマーの最低賃金法は、2年毎の賃金見直しを定めており、2020年には更に増額される予定である。
従って、「安価な労働力」というものが果たしてどこまで実際に魅力的かつサステナブルなものかについては相当な疑義があることになる。
以上の他にも、書籍や資料によっては、「豊富な天然資源」などという意味不明な記載も見受けられる。これも、くどいようだが、それが一体自社のビジネスに何の関係があるのか、という話だ。
我々はビジネスマンであって、評論家では無い。役職の高い人ほど評論家染みる傾向があるので要注意だ。漠然かつ表面的な話では無く、具体性を持った進出・投資の理由付けを持つことが重要だろう。
<ミャンマー市場の本質的な特徴とは何か>
ここまでの説明にご納得頂けたか否かはわからないが、少なくとも伝えたかったメッセージとしては、一般論でビジネスジャッジをするということの不毛さだ。残念ながらこうした理由を列挙した進出は、ウソみたいな話だがこれまで実際多く存在した。もちろん私のようなコンサルタントにもその責任は十分あるだろう。
おそらくそれらは、「進出ありき」の説明付けであった可能性もある。ミャンマー訪問を通じて、企業トップが直観的に面白そうという心証を得た後、その鶴の一声に、忠実な部下が必死で伴奏を交えて、何となく曲にしていく作業のようなものであったのかもしれない。
ただ、ミャンマーへの投資を誘う仕事をしている私が言うのもおかしな話だが、こうした「進出ありき」の議論は明確に避けた方が良い。苦しむのは後々現場を任される人たちだ(これはもちろんミャンマーに限った話では無いが)。
それでは、ミャンマー市場の本質的な特徴とは一体どこにあるのだろうか。当然これ自体も一般論になり、かつあくまでも個人的な意見とはなってしまうが、ProsとConsをシンプルに一つずつ挙げたい。
Pros(良い面) : 「未だ競争環境が緩く、多くの事業領域においてマーケットリーダーになれる可能性が残されている」
Cons(悪い面) : 「インフラ等の未整備により、短期的な収支均衡を図ることが困難」
ミャンマーでアドバイザリーの仕事を7年近く続けているが、これが若輩者なりの結論と言える。
まず、ミャンマーの「プラス面」について説明したい。
2011年の民政移管まで、ミャンマーは実質的な鎖国を半世紀近くに亘って続け、その意味では開国してからまだ日が浅い。また、東南アジア他国との比較感で見た時、ミャンマーの市場規模はやはり小さく、多額の投資が一気に向かうということにはなりづらい。これらを理由として、未だ手が付けられていない事業領域は多岐にわたる。
例えば、ベトナムやフィリピンも同様に途上国ではあるが、ミャンマーの先を少なくとも10年は行っている。現地を見回して、まだ手が付けられていない分野を探すのは大変だろう。しかし、ミャンマーはこの点が大きく異なる。
「誰もやっていなければ即ち成功出来る」などという甘い話をするつもりは全く無いが、仮に事業が軌道に乗り市場における認知が進めば、マーケットリーダーとして市場全体の将来的な成長の果実を享受することが出来るかもしれない。仮に、日本の中小企業であったとしても、やりようによってはその可能性は十分あるのがミャンマーだ。少なくとも他国との比較感で言えば、その確率が高いことは間違いない。
次に、ミャンマーの「マイナス面」について。ネガティブな話が並ぶんでしまうが、敢えてお伝えしたい。
一言で言えば、「少ないレベニュープールの中で高コスト体質になりやすい」環境だ。仮にマーケットリーダー的な存在になれたとしても、収支均衡には時間がかかる。従って、資金余力や長期のコミットメントが無い場合は、そもそも始めるべきでは無いだろう。
ミャンマー進出の検討の際に多くのケースで躓くのが市場規模(マーケットレベニュープール)の推定だ。統計データが圧倒的に不足していることに加え、産業自体が無い場合はそこに実際の需要があるのかさえ分からないケースも多い。頭を柔軟にして、一定の市場規模の推定は必ず行った方が良いが、結果として出てくるレベニュープールはおそらく相当低いものである可能性が高い。一人当たりGDPが1,200米ドル近くの国であるわけだから当然ではある。
一方、コスト面では、意外なことに周辺国に比べて総じて高くつく場合が多い。人件費や物価が安いはずのミャンマーでこれは一体何故なのか?
理由は多岐に亘るが、代表的なものとして、(1)駐在員コスト、(2)家賃コスト、(3)インフラ未整備コスト、の3つを取り上げる。
(1)は、現地のマネージメントとして派遣する日本人の駐在員コストだ。人件費には、通常の日本の給与・社会保険に加え、現地勤務に対する危険地手当(ハードシップ)が入る。また、住居費に加え、駐在員に多くの場合支給される車(ハイヤー)、ビザ代、保険料、日本への渡航費(年に2,3回程度)等が加わる。家族がいる場合にはこの金額が更に膨れ上がり、子どもの教育費も大部分を会社負担で行うケースが多い。この結果、大企業ともなれば、年間のコストは4000万円を超えるケースも珍しくない。
(2)は、高留まる不動産価格に伴って生じる家賃負担だ。これは、上記の駐在員の住居費のみならず、オフィス家賃についても当然当てはまる。実際にオフィス賃料が現地法人のP/Lを相当痛めているケースは少なくない。
※ ヤンゴンの不動産事情については、少々古い記事だが以前掲載したこちらをご参照。
オフィス家賃は2015年頃をピークとして、現状下落トレンドにはあるが未だ割高感は強い。ヤンゴンの好立地のオフィス家賃はピーク時の平米90米ドル(月間)程度から足元50米ドル以下まで下落はしている。業種業態にもよるが、オフィス家賃としては月間総経費の20%以内程度には収めたいところだ。
最後の(3)の「インフラ」というのは、道路・橋、或いは電力・エネルギーだけでなく、社会インフラ全般の未整備を意味している。法務インフラについては、投資法・会社法の成立により概ね周辺国とのレベル感の差は無くなったが、経営の現場では許認可取得、税務対応、各種外資規制等により、それらを賄うための金銭的・時間的負担が余分にかかる構造にある。
以上により、ミャンマー現地法人の収支構造は総じて赤字先行となりやすく、それが短期的に解消することが難しい場合が多い。ミャンマーの成長を前提とした本社主導のバラ色の事業計画をこれまで多く見てきたが、同時にそうした非現実的な計画の前でやる気を失う現地スタッフとも多く接してきた。これは誠に不幸なことだ。
ミャンマー事業の収支構造が如何に無理筋であるかのイメージを持って頂く為に、 関心があれば以下もお読み頂きたい。
<参考:ミャンマーの収支構造の典型的な無理ゲー>
想像してみて頂きたいのは、例えば、以下のような企業の収支構造だ。
わかりやすくサービス業の会社とする。従業員は50名で、うち40名がフロント(収益部門)で、10名がミドルバック(間接部門)。人件費は一人当たり平均月500米ドル、ボーナス込みで14カ月分換算として年間7,000米ドル。全社ベースの人件費は、年間7,000米ドル×50名で350,000米ドルとなる。人件費以外の経費はここでは無視。一方、収益面はフロントの人が人件費の倍となる月1,000米ドル(年間12,000米ドル)の粗利を稼ぐとする。この場合、40名×12,000米ドルで年間の粗利は480,000米ドルとなる。35万ドルのコストに対して48万ドルの粗利ということで、なかなかうまく行っている会社のように見える。さて、ここで抜けているのは何か。そう、マネージメントの人件費だ。日本人駐在員のコスト(人件費、福利厚生、住居、車、渡航費等)は企業により異なるが、高いところでは年間40-50万ドル(商社や銀行等)、低いところでは20万ドル程度だろう。上記の収支に仮に20万ドルが加わるとすると、当然赤字になる。日本人1人で上記の50名のミャンマーローカルの所帯をマネージするのは現実問題、生半可なものでは無い。突き詰めると、無理ゲーだと気付くことが多いだろう。
<ミャンマーは上級者向けのマーケット>
海外事業の開始は第二創業とも言われる。ただ、一方で日系企業の中でそれほどの覚悟を持って望んでいる企業は実際稀だろう。海外展開には甘い気持ち、無難にこなそうというスタンスは通じないケースが多い。特に、ミャンマーのようなヘッジしようの無いリスク満載の国では尚更だ。肝を据えて取り組まねば、上記のミャンマーの特性(良い面)は決して活かせない。
ミャンマーは「上級者向けのマーケット」と言われることがある。実際、収支状況に関するデータ上も、ミャンマーは東南アジアの中でも最も日系企業が苦戦している国であることが示されている。
事業規模(スケール)を追わない限り間接費が薄まらない一方、スケールすれば日系企業こだわりのクオリティコントロール(品質管理)が利かなくなる。そのジレンマの中でも、やはり日本の本社は自分たちのスタンダードを曲げれないケースも見られる。
「勝ちに不思議の勝ち有り、負けに不思議の負け無し」というが、ミャンマーでこれまで起こった失敗事例には多くの示唆が含まれている。他社の失敗事例を踏み台にしてでも、事業の成功に結びつけていくことが重要だろう。
最後にもう一点だけ付け加えさせて頂くと、ミャンマーへの進出検討は、「自社の本質的な強み」を改めて考える良い契機になるかもしれない。何故、こんな事を敢えて書くかと言えば、「自社の付加価値の源泉が何であるか」を、社員はともかく役員の方でも考えることすらしていないことがあり得るからである。
日本或いは他国ではうまくいくことがミャンマーではそうもいかないことが多い。ただ、自社の本質的な強みを現地マーケットに適合させることが出来れば、最悪の事態は必ずや避けれるはずだ。
関連記事 : ミャンマー進出・投資のポイントを本気で解説(第2回:参入市場の構造を理解。市場エコシステムの中でのポジショニングとは) 2020年8月9日
関連記事 : ミャンマー進出・投資のポイントを本気で解説(第3回:人事が成功の可否を決める。新興国ビジネスを経営出来る本社体制とは) 2020年8月11日
関連記事 : ミャンマー進出・投資のポイントを本気で解説(第4回:パートナー選定ミスは致命的。ミャンマーでの合弁会社設立の要点) 2020年8月15日


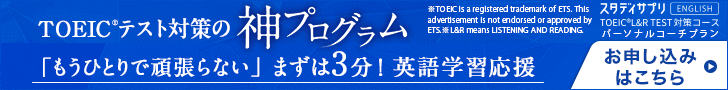



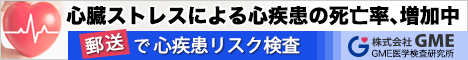













この記事へのコメントはありません。